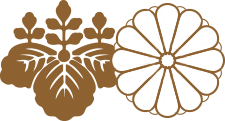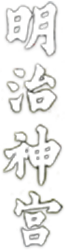明治天皇と昭憲皇太后
昭憲皇太后は、かつて「夫婦有別」と題されて、
むつまじき中洲にあそぶみさごすら
おのづからなる道はありけり
とお詠みになりました。皇后はこのお歌のように、仲むつまじい夫婦にあっても自ずから分別はあるものとお考えになり、夫婦のあるべき姿を、身をもって示されました。
末松謙澄は次のように述べています。
天皇は御製を詠まれるときなど、うっかり文字をお忘れになったときには、皇后にお尋ねになる。するとお慎み深い皇后は、熟知されている文字でも決してすぐ軽々とお答えにはならず、常におそばにある辞書をお開きになり、「その文字は辞書にこのようあります」と答えられた。
両陛下はご昼食とご夕食の際、常の御座所の二の間でテーブルに向かい合って楽しく召し上がりましたが、皇后は決して天皇の真正面ではなく、少し下手の方にお座りになりました。
ご昼食の時間は正午と定められていましたが、天皇のご公務が忙しく、午後の2時、3時まで延びてしまうことも少なくありません。このような時も、皇后は静かに天皇のお帰りをお待ちになりました。両陛下が一日の中で最も楽しく、くつろいだ一時を過ごされるのは、やはりご夕食の時です。その際皇后は、典侍をはじめ女官をお招きになることもありました。
明治天皇は皇后を「あなた、あなた」と親しくお呼びになるのが常でしたが、皇后をお労(いたわ)りになるご様子も、たいへん睦まじいものがありました。お身体のご丈夫でなかった昭憲皇太后は侍医のすすめで、冬になると気候の暖かい葉山や沼津の御用邸にしばしば転地療養をなさいました。その際には、使いの者を通してその土地の珍しいお菓子や産物を、明治天皇に献上されました。天皇もまた皇后に使いを立て、いろいろとお心のこもった贈り物をされましたが、ある時、天皇はご自身で見立てた人形に名前を付け、お使いとして贈られたこともありました。天皇からのお使いがご伝言を申し伝える際には、皇后はお敷物を外され、両手を畳につけてお聞きになるのでした。転地中、週に一度は必ず両方からお使いが出るので、両陛下ともお便りをお待ち兼ねのようであったということです。また御用邸でのご起床・ご就寝なども、決して意のままにされるのではなく、皇居から「聖上ただいまご機嫌よく御寝(ぎょしん)」との電話があったことをお聞きになるまでは、何時になっても正座のまま遥かに皇居の方に向かわれ、おやすみのご挨拶をされてはじめて御寝所に入られました。
天皇が各省から届けられる書類の袋(奏上袋)を保存され、詠草をしたためられる際にお使いになったことは有名ですが、皇后もまた、天皇の質素倹約のご精神をお手本とされ、お歌をお詠みになる際には、すぐに紙にしたためられることはせず、硯箱の蓋にわざわざ造らせた紙石盤に下書きし、何度もお気に召さないところを修正されたうえで、はじめて紙にお書きになったそうです。
こうして一事が万事、すべてを天皇と御心をひとつにご日常を過ごされたことは、おそれながら「夫唱婦随(ふしょうふずい)」の模範を示されたものと思われます。
【石盤附御蒔絵硯箱(明治神宮所蔵)】