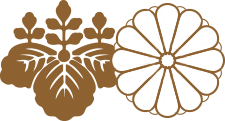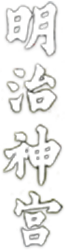明治天皇崩御
明治45年7月19日、天皇の御不例(ごふれい=ご病気になられること)が発せられました。
皇后は洋装のままで天皇の枕辺にお座りになり、昼夜をわかたず薬をすすめ、またうちわで風を送られるなど、懸命に看護なさいました。天皇が崩御された30日まで、ただ一回お髪上げに病室を退かれたほかは、ひとときも天皇のおそばを離れませんでした。その様子は全国の新聞で報道され、国民は皇后のご淑徳の深さにあらためて敬意を表しました。
ところで、天皇陛下の診察は勅許がなければお仕えすることができませんでした。しかしご病状が進み、当時、名医といわれた三浦勤之助・青山胤通(たねみち)両博士が内々に参内したものの、すでに意識混沌(こんとん)とされお許しの言葉を承ることはできず、「もしお許しを受けずに両博士が拝診して万一陛下がお気付きになったら、お叱りはいかばかりか」と、宮内大臣すら恐ろしくて踏み切れずにいました。
この時皇后が、
「聖上(おかみ)はお許しにならぬとは言っていない。私がすべて責任をもちますから早く申し付けるように。」
とご決断されたため、ようやく拝診のことが決定したということです。
20日には、伊勢の神宮にお使いを遣わされご平癒を祈願されましたが、その甲斐も虚しく30日、天皇はついに崩御されました。
皇后のご悲嘆の深さはたとえようもありません。
昭憲皇太后はか弱いお身体で、10日以上にわたり寝ずの看護にあたられたため、御髪は乱れてすっかり気色を失い、お顔色も衰えてしまわれました。
そばに仕える者は誰もが涙をこぼして、崩御を悲しみ、皇后に深くご同情申し上げました。
山川三千子は『女官』のなかで当時の様子を次のように述べています。
話は明治天皇崩御の時のことでございます。女官全部が一人一人、皇后宮様にご挨拶申し上げました時は、「本当に恐れ入った御事で」と、はっきりお答えになって、あまりお涙さえお見せになりませんので、私は何か不思議なような気が致しました。そして数時間後、お召し替えのために御休所(ご自分のお部屋)へお供いたしました時、
「私の悲しいのは誰よりも一番でしょう。しかし私が泣きくずれていては、後のことがどうなると思いますか」
と仰せになって、ハンカチーフをお顔にお当てになりました。それを拝見して私は何とお答えの仕方もなく、ただ深く頭を下げておりました。
また元侍従職出仕で後に神宮大宮司を勤めた坊城俊良(ぼうじょうとしなが)は、当時を次のように振り返っています。
明治45年夏、天皇がご発病あらせられた時には、暑さにめげず、皇太后は昼夜の別なく御枕頭(ちんとう)でご看病を遊ばされ、うろたえる女官をよくご指揮遊ばされたことは、まだ記憶にはっきりと残っている。
御病の軽いうちは、天皇はよく私をお呼びになり、御用をお命じになった。ご重体になるにつれて、お言葉も途中で切れがちになり、去就(きょしゅう)に困った時もあった。その時皇后は落ち着いて、
「またお呼びになるまでは退いているように」
との助け舟を出していただいて、ほんとに助かったこともあった。平素ご用を承る時は、仰せがないうちは、どんなにお話が永く切れても退いてはならぬことになっていたからである。
しかしついに崩御の時が到来したのである。大正天皇は直ちに践祚(せんそ)され、御父陛下の御遺骸を拝されてから、皇太后にご挨拶遊ばされた。この時、皇太后はご御挨拶をお受けになる位置を、大正天皇の下にとろうとなさった。しかし大正天皇は、それをお聞き入れなく何度か譲り合われる光景を拝した。その場に居合わせた女官達は泣きだしてしまった。それは践祚の瞬間から御位置の上下が定まってしまったからである。
皇太后は静かにやさしく、大正天皇が上位におつきにならなければならぬ事をおさとしになって、初めて天皇も渋々ご承知になりご挨拶があった。この光景が今なお眼前にありありと思い浮かぶ。
【聖徳記念絵画館壁画「大葬」】