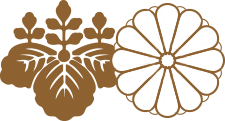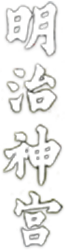歌の師・高崎正風
薩摩藩出身の高崎正風(たかさきまさかぜ)は、明治初年から両陛下に仕え、長く宮中の御歌所長を勤めた人物です。かつて皇后は高崎に、歌を詠む際の心がけについておたずねになりました。高崎は、
「素直で飾らない、心のありのままを、三十一文字(みそひともじ)に綴るのがまことの歌というものです。歌は、正直につくれば決して難しいものではありません」
とお答えしました。
ところがある時、今度は高崎の方から皇后に次のような質問を申し上げました。
「私は今『月下述懐』の題で歌を作っているのですが、下の句が落ち着かず、困っております」
すると皇后は、にこやかなご表情で、
「あなたは以前、歌は素直に詠むことだと申していたではありませんか。そうであれば一首の歌にそのように苦しむことはないでしょう」
とおっしゃいました。高崎はハッとして御前を退き、帰宅後早速、心を正して一気に歌を作ってみると、自分の心情にピッタリと合った歌が出来たということです。あまりの嬉しさに、すぐさま皇后にこのことを報告したところ、皇后は、
「あなたが言ったことをそのまま注意しただけですよ」
と話され、高崎はたいへん感激したということです。
また皇后は葉山御用邸で静養中、高崎正風の別荘にお出ましになり、亡き母の肖像画をご覧になって、
「今日思いがけず、卿の母に面会でき満足に思います。卿は頬から口の辺りが母に良く似ています」
とおっしゃいました。高崎はこの時の感激を次のように歌に詠んでいます。
おきあまるこの下露の御恵みに
枯木の母ぞうるほひにける
明治37年8月、嗣子(しし)高崎元彦(海軍少佐)が戦死した際、両陛下は菓子を賜って弔慰されましたが、高崎はその時の胸中を和歌で表しました。
大君のみをしへ草をしをりにて
さきだちし子を何か嘆かむ
皇后は高崎のことを哀れみ、9月8日に次の二首を賜ったのでした。
くにのためすてしこの身ををしむにも
まづおもはるるおや心かな
千代ふべきうまこを杖に呉竹の
すくよかにして御代につかへよ
高崎はこのお心遣いに、歌をもって心から感謝申し上げました。
児ゆゑにはなかぬ袖をもぬらしけり
国の母そのもりの雫に
くれ竹のこのこをもまたおほしたてて
ささげまつらむ君のみたてに
明治45年2月28日、高崎正風が77歳で逝去すると、両陛下はそれぞれに葬儀の資金を賜り、丁重に弔われたのでした。
昭憲皇太后が崩御されて後、故高崎元彦の未亡人は、
父も生前によく申しましたが、陛下には常々、孫のことについてお言葉をくだされ有り難いしあわせである、よく下々の心をお察しくだされて、年寄のために孫の事をお尋ねくださる、正光もこの有り難さを忘れてはならぬと教えました。父が脊髄(せきずい)を患いました折には、お使いをくだされ、孫へと言って人形と箱入りの犬を二個くださいました。父へのお見舞いをくださるのさえ有り難い幸せですのに、同時に子供にも下され物がありましたのは、何とも申しようのない光栄です。
と述べて、皇后のお心遣いに感謝のまことを捧げています。
【毛植の犬(明治神宮所蔵)】