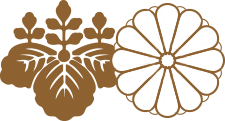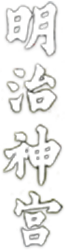たぐいないご文藻──お歌に寄せる御心
皇后の秀でたご天分は、とくにお歌のなかに遺憾なく発揮されました。3万首ものお歌を残され、今日でも明治天皇とともに古今たぐいない歌聖と仰がれています。
皇后はご日常、側近に奉仕していた八田知紀(はったとものり)、高崎正風(たかさきまさかぜ)、税所敦子(さいしょあつこ)、小池道子らとともにお歌の道に励まれましたが、「仰せごとによりて」と題して、つまり天皇のご指示をうけて詠まれたお歌も少なくありません。これらは即詠と思われますが、格調の麗しいお歌ばかりです。
たとえば明治16年には「おほせごとによりて月前霧を」「くもりがちなる夜おほせごとによりて空をあふぎて」とそれぞれ題して、
さぎりたつこよひも月のさやけきは
君がみかげのそへばなりけり
みこころにかからざりせばうきぐもの
ひまゆく月のかげもみましや
という2首を詠まれました。両陛下はこのように常日頃ご覧になるもの、お耳にされるものをことごとく素材にし、詠歌を楽しまれたのでしょう。
この即詠については次のような逸話が伝えられています。
明治30年、京都御所にご滞在中のある日、明治天皇は御所の勾欄(こうらん)に1匹の毛虫が這(は)っているのをご覧になり、
「ふとどきなやつだ。毛虫には昇殿を許しておらぬはずだが」
と冗談をおっしゃいました。
この時、そばでお聞きになっていた皇后はすかさず、
位あるまつさへ庭にたちぬるを
毛むしのぼれり板敷の上に
とお詠みになりました。秦の始皇帝が松に太夫の位をさずけたという故事にちなんだお歌と思われますが、この時の天皇の当意即妙なご冗談と皇后のご歌才とは、好一対をなすものといえましょう。
また、天皇は明治11、2年頃、詠史歌、つまり歴史上の人物を題材とした歌を作るよう側近の人々にお命じになりました。優れた詠史歌を作るためには、古今の歴史に精通しなければなりませんから、侍臣の多くは苦しみましたが、皇后は詠史にもひときわご才能を発揮されました。
たとえば「焚裘示倹(ふんきゅうじけん=皮衣を焚いて倹約を示す)」と題されて次のようにお詠みになりました。
燒きすてし雉の毛衣うらうへに
もとむる世ともなりにけるかな
これは中国の古代、晋の武帝が雉(きじ)の毛皮の美服を焼き捨てて、臣下に倹約の範を示したという故事によって、暗に華美を競う当時の世情をいましめられたものです。
さらに日本武尊(やまとたけるのみこと)の妃・弟橘姫(おとたちばなひめ)が、身を荒海に投じて海神(わたつかみ)の怒りを鎮め、尊のご生命を守護されたことを称え、
ふねの上に君をとどめて橘の
いまはとちりしこころをぞ思ふ
とお詠みになっています。
明治天皇はお歌に、
天地もうごかすばかり言の葉の
まことの道をきはめてしがな
思ふことありのまにまにつらぬるが
いとまなき世のなぐさめにして
と詠まれ、お歌の道にことのほか御心をそそがれましたが、このようにご文才に富まれる皇后こそは、まことに得がたい伴侶でいらっしゃったのです。
【御短冊】
白菊
咲きにほふすそ野のきくは不二のねに
あまりて落し雪かとそ見る