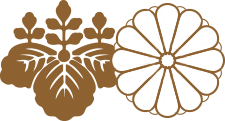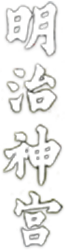天皇ご発病
明治45年7月20日、宮内省から天皇のご発病のことが発表になりますと、国内にはとたんに憂色の空気がたちこめ、国民は毎日宮内省の発表にかたずをのんでいました。
元侍従職出仕でのちに神宮大宮司をつとめた坊城俊良(ぼうじょうとしなが)は、当時のことを次のように振り返っています。
ご発病の夜、私はちょうど当直をしていました。いま思えばすでに2・3日前からご気分がすぐれず、御奥から御表への階段を昇られるのも、なんとなくおつらそうに見受けられましたが、その時はそれほどとは思い ませんでした。しかしご発病の日のご容体の悪さは、私どもの目にもはっきりと確認できました。けれども責任感の強い天皇は、いつも通り御学問所にお出ましになって、ご政務を執られ、定刻にお帰りになりました。
ところがご就寝になったとたん、大変な高熱で、ご意識すら充分でないようになりました。それからの宮中での驚きは申すまでもなく、国民がこぞって憂いの気持ちに閉ざされたのは、今更いうまでもありません。
皇后陛下(昭憲皇太后)、東宮殿下(大正天皇)同妃殿下(貞明皇后)をはじめ、女官や侍従のものは昼夜おそばを離れず、ひたすら一日も早いご快復をと力の限りを尽くしました。ご大患を報じる新聞号外が発表になりますと、国民が真心を尽くして神仏に祈り、宮城前にひれ伏してご快癒を願ったことは、日本国民でなければ考えられない尊い心の表れでしょう。
しかし、たとえ毎日侍医が発表するご容体がだんだん悪い模様であったとはいえ、まさか天皇が崩御になるということは誰一人として夢にも思いませんでした。とくに側近に仕えるものにはその自信が強かったのです。と申しますのは、あの立派なご体格、現に私の11年間の奉仕中、お風邪のためにお休みになったときでも、ごく軽いもので、それもわずか数回あっただけですから、普段からお強い天皇であられますので「いまに必ずお治りになる、いまにきっと……」とばかり思って、同僚のものともそう話し合っておりました。ですから崩御をうかがったときの驚きは、そうした自信が強かっただけに、いっそう痛切に感じました。
【聖徳記念絵画館壁画「不豫」】