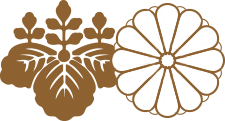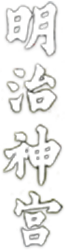副島種臣の誉れ
うつせみの世はやすらかにをさまりぬ
われをたすくる臣の力に
このお歌は天皇が明治40年にお詠みになったものですが、佐賀藩出身の副島種臣(そえじまたねおみ)もこのお歌のなかにあるような、天皇をたすけて国家と国民のために力を尽くした人物の一人です。
副島は明治元年3月に政府の参与、4年11月には外務卿(現在の外務大臣に相当する役職)となって維新当初の多難な外交問題を堅実に処理しましたが、征韓論問題を契機に国政から退いていました。しかし彼の人格や学識の豊かさが高く評価され、明治12年4月、宮内省御用掛一等侍講に任命されました。
以来、副島は毎週火曜日には天皇、木曜日には皇后に対して『大学』や『中庸』など中国の古典を中心に講義を申し上げましたが、翌年諸般の事情により宮中に出向くことをやめてしまいました。天皇は副島の進講が途絶えたことを不思議に思い宮内卿の徳大寺実則におたずねになりますと、
「副島は考える所があって、もしかすると侍講職を辞めるかもしれません」
との答えです。
その夜、天皇は侍補の土方久元を副島邸に派遣されました。出迎える副島に土方は、
「これは、陛下からのお手紙(宸翰=しんかん)です」
と手渡しました。そこにはおよそ次のように書いてあったのです。
卿は維新の時に多大な功績を挙げたが、私は今でもそのことを忘れてはいない。それゆえ卿を侍講の職に任命し、自身の修養のために力を貸してほしいと思った。しかし講義がはじまってまだ日は浅く、卿の教えを充分に吸収するにはいたっていない。最近卿は病気のために講義を中止しており、聞くところでは侍講職を辞めて故郷に帰ろうと思っているようだが、その話を聞いて愕然(がくぜん)とした。卿は何のために宮中に足を運んでいたのか。私は君主としての正しい道を学ぶ努力をたかが1年、2年で終えてはいけない、生涯にわたって学んでいこうと思っているゆえ、嫌がらずに指導をしてほしい。職を辞退して故郷に帰ることを許すわけにはゆかない。どうかこれからも、君主の道について講義をしてほしい。
手紙を読んでいた副島の手がみるみる震えはじめ、目は真っ赤になってボロボロと涙がこぼれ落ちました。そしてとぎれとぎれの言葉で土方にこう答えました。
「明朝宮中に参内し、陛下にお礼を申し上げます」
それ以降、副島は侍講職が廃止になるまで真心をもって天皇のそばにお仕えしました。
副島はお手紙に固く封をし、「死後も開封せず神棚に奉(たてまつ)れ」と遺言しました。しかし、副島の逝去後はじめて遺族によって開封されました。天皇からのお手紙とわかった一同は、驚きと緊張の中、おのずと姿勢を正し厳粛な態度で拝見したそうです。
【副島種臣】
出典:国立国会図書館「近代日本人の肖像」 (https://www.ndl.go.jp/portrait/)