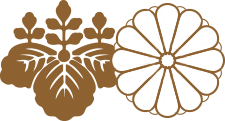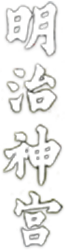11月1日から11月3日まで「秋の大祭」が行われます。
11月1日の鎮座記念祭では、鎮座百年大祭を記念して明治天皇の御製(ぎょせい)からつくられた神楽「常久(とこしへ)の舞」が舞われます。
また、11月3日の文化の日は明治天皇の御誕生日にあたり、宮中より勅使(ちょくし)が差遣(さけん)されて例祭が行われます。
大祭期間中は、「舞楽」や「能・狂言」などさまざまな伝統芸能が奉納されます。
- 11月1日(土)10:00
- 鎮座記念祭
- 11月2日(日)10:00
- 秋の大祭 第二日の儀
- 11月3日(祝)10:00
- 例祭
秋の大祭奉祝行事
- 11月1日(土)12:00
-
- 能・狂言
- 於:神前舞台
- 11月1日(土)15:45
-
- 三曲
- 於:神前舞台
- 11月2日(日)11:45
-
- 舞楽
- 於:神前舞台
- 11月2日(日)14:45
-
- 邦楽邦舞
- 於:神前舞台
- 11月3日(祝) 9:00
-
- 全国弓道大会
- 於:武道場至誠館第二弓道場
- 11月3日(祝) 9:00
-
- 合気道演武
- 於:西参道沿芝地
- 11月3日(祝)10:00
-
- 古武道大会
- 於:西参道沿芝地
- 11月3日(祝)11:00
-
- 百々手式(ももてしき)
- 於:宝物殿東芝地
- 11月3日(祝)13:00
-
- 流鏑馬(やぶさめ)
- 於:西参道沿芝地
- 11月3日(祝)15:00
-
- 薩摩琵琶
- 於:外拝殿
※雨天等により変更する場合があります。
11月1日(土)12:00 能・狂言 神前舞台

奉納/能楽協会
演目
半能「玉葛(たまかづら)」
旅僧が大和国長谷寺に参詣すると、小舟で初瀬川を遡る女性と出会って言葉を交わし、玉葛(たまかづら)の幽霊であることを仄(ほの)めかして消え失せます。
その夜、僧(ワキ)の弔いに引かれて玉葛の霊(シテ)が現れます。仏の救済を願いつつも恋の妄執(もうしゅう)に囚われ続け、いくたび払っても纏わり続ける乱れ髪に苦しみ、多くの男性達から想いを寄せられてきた生前の記憶を懺悔(ざんげ)し、執心を翻(ひるがえ)して過去の記憶と決別し、ついには成仏を遂げます。
狂言「成上り(なりあがり)」
初寅(新年はじめての寅の日)のめでたい日に、主人と鞍馬寺に籠もった太郎冠者は、眠っている間に、主人から預かった太刀を、すっぱ(詐欺師)に盗まれ青竹にすり替えられてしまいます。盗まれた言い訳にさまざまな「成上り」の話を並べていると、再びすっぱが現れ……。
【玉葛】
シ テ 金森 良充
ワ キ 梅村 昌功
笛 寺井 宏明
小 鼓 住駒 充彦
大 鼓 柿原 弘和
後 見 朝倉 俊樹
佐野 玄宜
地 謡 和久 荘太郎
東川 尚史
佐野 弘宜
金野 泰大
金井 賢郎
上野 能寛
【成上り】
シ テ 三宅 右矩
ア ド 三宅 近成
前田 晃一
後 見 金田 弘明
11月1日(土) 15:45 三曲 神前舞台

奉納/三曲協会
演目
山田流箏曲 「松上の鶴(しょうじょうのつる)」
・真磨琴会(ままごとかい)社中
雲井(くもい)に生い立つ松に宿る鶴を主題とした歌詞で、いかにも作曲当時(明治時代)の時代相を反映しており、これに山登万和(やまとまんわ=1853~1903年)が作曲しました。
生田流箏曲 「嵯峨の秋(さがのあき)」
・米川敏子(よねかわとしこ)社中
明治時代に大阪の菊末勾当(きくすえこうとう)が作曲した、いわゆる明治新曲の初期のものです。詞章(ししょう)の典拠は「平家物語」の小督(こごう)(平安末期の女性。類稀な美貌の箏の名手だったと伝わる)が“想夫恋(そうふれん)”を奏するところを中心に描写していますが、曲のねらいはむしろ手事部(てごとぶ)にあり、高・低二部の箏の合奏の器楽性を発揮させることを目的としていると思われます。
11月2日(日)11:45 舞楽 神前舞台

奉納/楽友会
「振鉾(えんぶ)」
周の武王が殷(いん)の紂王(ちゅうおう)を討って天下の平定を誓った様を象(かたど)ったものといわれています。舞楽会のはじめに奏するのを例とし、天地の神々や先霊を祀(まつ)る意味があるとされています。左右一人ずつの舞人が舞台に登り、笛、太鼓及び鉦鼓(しょうこ)のみの演奏により舞います。それぞれ襲装束(かさねしょうぞく)、鳥甲(とりかぶと)を纏(まと)い、右肩を袒(ぬ)ぎ、鉾を両手に持って舞います。
「甘州(かんしゅう)」(左方の舞)
唐の玄宗(げんそう)皇帝(在位712~756年)の作と伝えられています。甘州(かんしゅう)は国の名で、その国に海があり甘竹が生えており、その竹の根元には毒虫が多くて切れないと言われ、そのために人が多く亡くなりましたが、この曲を奏して船に乗って来て竹を切れば人を害さなかったと伝えられています。それはこの曲が金翅鳥(きんしちょう)の鳴き声に似ているからと伝えられています。左方の四人舞で、襲装束の諸肩(もろかた)を袒いで舞います。この舞は「種子播手(たねまきて)」という甘州独特の舞手があります。
「納曽利(なそり)」(右方の舞)
高麗(こうらい)から伝わった舞曲ですが、由来などは不明です。「双竜舞(そうりゅうまい)」といわれ、雌雄(しゆう)の竜が楽しげに遊ぶ姿をかたどったものと伝えられ、昔は相撲など勝負事の折に、勝者を讃えて奏したとされています。右方の二人舞で、舞人は絢爛(けんらん)な打ちかけの裲襠装束(りょうとうしょうぞく)を着け、面を被り、右手に桴(ばち)を持って、破(は)および急(きゅう)を舞います。
「長慶子(ちょうげいし)」
源博雅(みなもとのひろまさ=980年歿)の作といわれている名曲で、慶祝の意を表す曲とされ、慣例として舞楽会の結びに舞楽吹(ぶがくぶき)で奏されますが、曲だけで舞はありません。
11月2日(日)14:45 邦楽邦舞 神前舞台

奉納/日本舞踊協会、長唄協会
演目
長唄「外記猿(げきざる)」
・出演者 西川 箕乃三郎
外記節(げきぶし)という浄瑠璃の「猿」という曲を長唄に移したのが「外記猿(げきざる)」という演目の名前の由来です。猿廻しが屋敷に呼ばれて、庭先で猿廻しの芸を見せる様子を踊りにしたものです。実際には猿は出てこないところをそれらしく見せるところが舞踊家の芸の見せどころです。
長唄「老松(おいまつ)」
・出演者 吉村 輝和
謡曲の「老松」に取材したもので、曲名が示す通り、老松のめでたさから唄い始め、松にちなんだ風物が表現されます。渋さ、華やかさがうまく配分されていて、格調の高さの中に洒落た雰囲気も楽しめます。踊り、演奏ともに技巧が要求され、それが聞きどころ、見どころとなっています。
【唄】
杵屋 君三郎
杵屋 六昶俉
杵屋 喜太郎
【三味線】
杵屋 新右衛門
杵屋 彌太郎
杵屋 佐助
【囃子】
小鼓 堅田 喜三郎
住田 福十郎
太鼓 堅田 新一朗
大鼓 梅屋 喜三郎
笛 福原 百貫
11月3日(祝)9:00 全国弓道大会 武道場至誠館第二弓道場

奉納/全日本弓道連盟
全日本弓道連盟会員約1,000人以上が参加する大会で、全員が一手(二射)奉納いたします。
11月3日(祝)9:00 合気道演武 西参道沿芝地

奉納/日本光輪会
合気道は、旧大日本武徳会が柔道や空手道とは別に、総合実践武道として創設したものです。
11月3日(祝)10:00 古武道大会 西参道沿芝地

奉納/日本古武道振興会
かつては30種ありましたが、現在残っているのは十数種です。明治神宮では、十手術、薙刀術、砲術、鎖鎌術など珍しい武術が奉納されます。
11月3日(祝)11:00 百々手式(ももてしき) 宝物殿東芝地

奉納/弓馬術礼法小笠原教場
百手式とは、10人が十手ずつ(矢2本が一手)射るところからきており、大きな祝典の際、神を勧請し、弓をもって祈念する儀式です。
11月3日(祝)13:00 流鏑馬(やぶさめ) 西参道沿芝地

奉納/大日本弓馬会
流鏑馬の起源は、欽明天皇が宇佐神宮の神前で天下泰平、五穀豊穣の祈願し、馬上から3つの的を射させられた矢馳馬(やばせめ)神事にさかのぼります。
明治神宮では大正9年、鎮座奉祝流鏑馬が武徳会により奉納され、昭和7年以降は全日本弓馬会より毎年奉納されました。昭和20年に一度中断しましたが、同28年に復活し、今日に至っています。
11月3日(祝)15:00 薩摩琵琶 外拝殿

奉納/友吉鶴心
演目
「敦盛(あつもり)」
壇ノ浦(だんのうら)の戦いから840年。その1年前、若き平敦盛(たいらのあつもり)卿は須磨(すま)で最期を迎えるのでした。
明治天皇も好まれてお聞きになられた題材の一つです。
10月25日(土)~11月23日(祝) 菊花展 正参道

奉納/各菊花会奉納団体
戦前は、11月3日の明治節を中心に各会派の奉納がありましたが、一時中断しました。昭和27年、明治天皇御生誕百年祭を機に、復活しました。